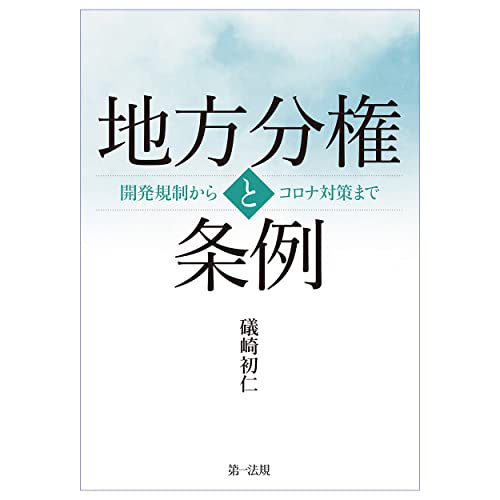年末は休みが短いもののオフにするぞ,と思ってシャットダウンしたらなかなか再起動できないままに1月も半ばになってしまいました。大学行政関係の仕事とルーティンの調査をやっているだけでアップアップという感じですが,リハビリを兼ねていただいた本の紹介を。ここのところ政治史の研究書をよくいただいておりました。
青山学院大学の小宮京先生からは『語られざる占領下日本』を頂いております。ありがとうございます。ハーバード大から内務省にノンキャリとして入って戦後は警察のトップに行った谷川昇,戦後直後の知米派としての三木武夫,河井弥八日記から見るフリーメイソン,そして小説吉田学校と田中角栄,とどれも非常に興味深い4つの章から,これまでに十分明らかにされてこなかった戦後日本の苦闘について論じるものです。個人的には三木の章が面白かったです。三木があまり英語をしゃべるイメージはなかったのですが,アメリカ滞在経験を軸にGHQとつながっていくというのはあんまり考えたことがなく,従来とずいぶん違う戦後史の見方のもとになると思いました。やはり従来といえば,白洲次郎もありますが,宮沢が英語通として出てくるイメージが強いと思うのですが,本書ではそんな感じで宮沢が出てくることはなく,自分自身が持っているイメージは「保守本流」の宏池会(というか文書を残していった官僚なのかもしれません)が中心に形成されているんだろうなあという感じを受けたところです。
大東文化大学の若林悠先生からは『戦後日本政策過程の原像』を頂きました。ありがとうございます。こちらは修士論文をベースにしたものということですごいですね。前著は気象行政に注目した行政史,今回は海運(計画造船)に注目した政策史ということで,必ずしも盛んに研究されるテーマではないわけですが,行政史・政策史における意義付けが明確にされているうえで,非常に手堅い資料分析をされているもので興味深く読みました。社会の側から政府に対して何かを求める運動が生じ(この場合は造船のための資源配分),それが政策過程の中で制度化されていく過程を描き出しているわけですが,意義の一つとして以下のように「議員・政党の介入」「非難回避」という本書の分析視角の有効性が挙げられているわけですがこれは現代においても非常に示唆的だと思います。今ってそういう「運動」はあんまりないのかなあ,どうなんだろうと思っていたところですが,「アベノミクス」はそうなのかもしれません。
「議員・政党の介入」の視角が,制度や政策に対する既存秩序を流動化させ再編成を図る政党側の論理(政治の論理)を象徴するものであり,「非難回避」の視角が秩序を合理的に維持しようとする官僚制側の論理(行政の論理)を象徴するものとすれば,二つの分析視角を用いることは,政治と行政の交錯過程を顕在化させるうえでも有益であった。
連想ゲームみたいにやや飛ぶのですが,科研プロジェクトでご一緒している帝京大学の軽部謙介先生からは『アフター・アベノミクス』を頂きました。歴史資料に基づく政治史というよりはジャーナリストとしてインタビューや公表された資料などを基にこの10年の「アベノミクス」を追跡されてこられた三部作の最後となります。最後は安倍総理の襲撃事件で幕が閉じるものとなっているわけですが。本書で描かれている過程は,アベノミクスがまさに既存の制度や政策を流動化させる運動であり,政治の側で金融から財政へと力点が変わったり,インフレ目標やPB目標の扱い方も変化させる一方で,行政の側が何とか平仄を合わせながら秩序を見出していこうと模索しているもののように読めました。
次に,版元の吉田書店から,稲吉晃先生の『港町巡礼』を頂きました。ありがとうございます。「港町からみた政治史」ということで,15の港町が一章ずつ取り上げられています。僕自身『領域を超えない民主主義』で港湾都市を扱っているわけですが,そこで出てくる函館・下関・大阪が扱われていますし,しばしば調査で関わりのある(あった)神戸や長崎といった都市が出てくるのも興味深く読みました。つい自分の本に引用するならどの辺だろうか,とか言う目線で読んでしまうわけですが,下関が北洋漁業の基地で,マルハニチロがらみで函館ともつながりがあるというのは十分に理解していなくて,それを知っていたらもう少し書くことができたかも…と思ってしまいました。最後のところで,港が国内政治と国際政治をつなぐ重要な要素であったものの,中央の政治過程で必ずしも重要な位置を占めたわけではなく,地方において政治と経済の狭間にいる企業家や地方政治家が重要になる特異性があるというのは面白い指摘だと共感しました。だからこそ地方政治のテーマにもなるのだろうというようにも思います。
次も吉田書店さんですが,帝京大学の渡邉公太先生から『石井菊次郎』をいただきました。渡邉先生はすでに研究書として石井菊次郎を中心に第一次大戦期の外交についての著作があるわけですが,今回はその中心であった石井の評伝を書かれています。僕自身の知識は(前も似たようなこと書いてますが)「石井・ランシング協定」の名前くらいしか知らないわけですが,本書では,陸奥宗光・小村寿太郎という戦前の外交家を引き継ぐ存在として描かれています。有名な協定自体,本書の真ん中くらいに出てくるものであって,石井がその後国際連盟や軍縮交渉などマルチの国際交渉で活躍しつつ,満州事変では「転向」とも批判されるような満州国擁護を展開していくところも描写されていきます。優れた外交官が国際協調を志向しつつも,自国の国益擁護が中心的な主張になっていくところは,あとがきにもあるように,国際平和の維持の難しさを示すものであるようにも思います。
こちらも帝京大学の中谷直司先生から『国際関係史の技法』を頂きました。ありがとうございます。国際関係史・外交史の方法論についての教科書で,理論的な説明だけではなくて,文書をどう使うかとか,検索の仕方や文献リストの作り方,具体的なメモやノートの取り方・使い方など実践的な方法についても触れられています。4章は1941年のアメリカの対日政策の解釈を具体的な事例にしていて,まさに上述の石井菊次郎の後半部分で対象としているところとも重なってくるものでした。自分もあるいは自分が指導している学生もなかなか国際関係史を直接研究することはなさそうですが,参考にさせていただきたいと思います。
昨年末にも紹介しましたが,東京大学の牧原出先生からは『田中耕太郎』を頂きました。ありがとうございます。東大教授・文部大臣・参議院議員・最高裁長官・国際司法裁判所判事,というなんかすごいキャリアを歩んだ田中耕太郎の評伝です。特に戦後の最高裁長官時代の業績で,「反動」という評価がされることもあるわけですが,本書は田中をカトリックの信者というバックボーンをもつ独立した「自由主義者」としてそれぞれの仕事を描き出す,非常に興味深いものとなっています。日本政治という観点からは,文部大臣・参議院議員から最高裁長官,という辺りが面白いわけですが(今ではたぶんあまり考えられないキャリアだし),本書の白眉は国際司法裁判所判事時代の記述にあるように思いました。大臣も議員も最高裁長官もやった人が,若干畑違いで,しかもそれまでの権威もあんまり通じないようなところで仕事をするっていうのは想像するだに大変のような気がしますが,そこで法律家として,独立した個人として仕事をしていくところを描くのは,本書の「自由主義者」としての田中像を説得的なものにしているように感じるところです。
とりあえず最後(長い…)ですが,甲南大学の三谷宗一郎先生から,『戦後日本の医療保険制度改革』を頂きました。ありがとうございます。医療保険制度改革の歴史については,実は自分自身も論文を書いたことがある分野でもあって,とても興味深く読みました。制度改革を議論するときに,官僚として参照する「政策レポジトリ」があり,それを医療保険制度に関わる代表的な官僚であった吉村仁氏や和田勝氏が関わりながら作っていたというのはまさにそうなんだろうと思います。厚生官僚としては,やはり一元化というか負担の均霑への志向というのはあって,しかしながらすぐにそういうことはできないから(by吉村氏),その場をいかにしのぐ(大)改革をするか,ということが重要になるところがある,というのが浮き上がるように感じます。
本書の中心的なトピックではないのですが,医療保険制度改革が基本的に事務官の歴史になっているところが日本/厚生省らしいと感じるところがあります。現在のコロナ禍にもつながる問題ではありますが,専門家としての医系技官が制度改革とかで出てこないというのは重要な特徴だと思います。最後に少し唐突に出てくる入院事前審査の問題はまさにこの点と関連しているのではないかと思いましたが,医療行為への保険者的な規制をするという志向はもともと少なくて,この1990年代の事例はそれがスパッと抜け落ちることをうまく示唆したものであるように感じました。一元化が志向される一方で,保険者機能の強化みたいな話はなかなか出てこないわけですが,制度改革における医系技官の不在は,その背景に医療そのものをコントロールする意思と手段があまりない(意思はあってもお金を通じたコントロール)ことを際立たせるようにも読めました。